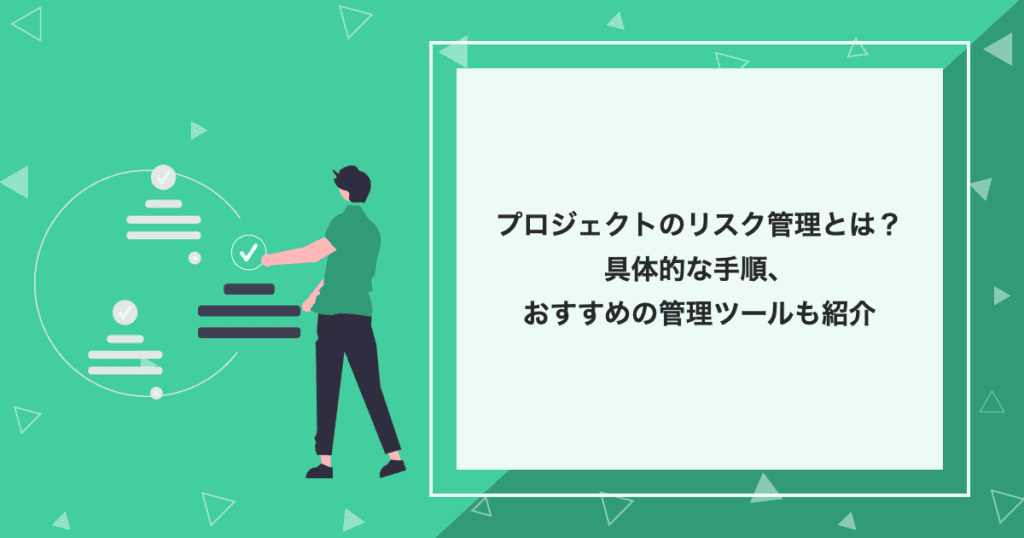
プロジェクト管理において、スケジュールの遅延やコスト超過、品質の低下といったリスクは避けられません。こうしたリスクを最小限に抑えるには、リスクの洗い出し・優先順位の決定・適切な対策の実施を計画的に進めることが重要です。
本記事では、プロジェクトにおけるリスクの種類や具体例、管理プロセスを詳しく解説し、効果的なリスク管理のポイントを紹介します。
また、後半ではプロジェクト管理ツール「Backlog」を活用することで、リスク管理を効率的かつ効果的に行える理由を詳しく解説します。リスク管理の精度を高め、プロジェクトをスムーズに進めるためのヒントを提供するので、ぜひ参考にしてください。
目次
プロジェクトにおけるリスクとは
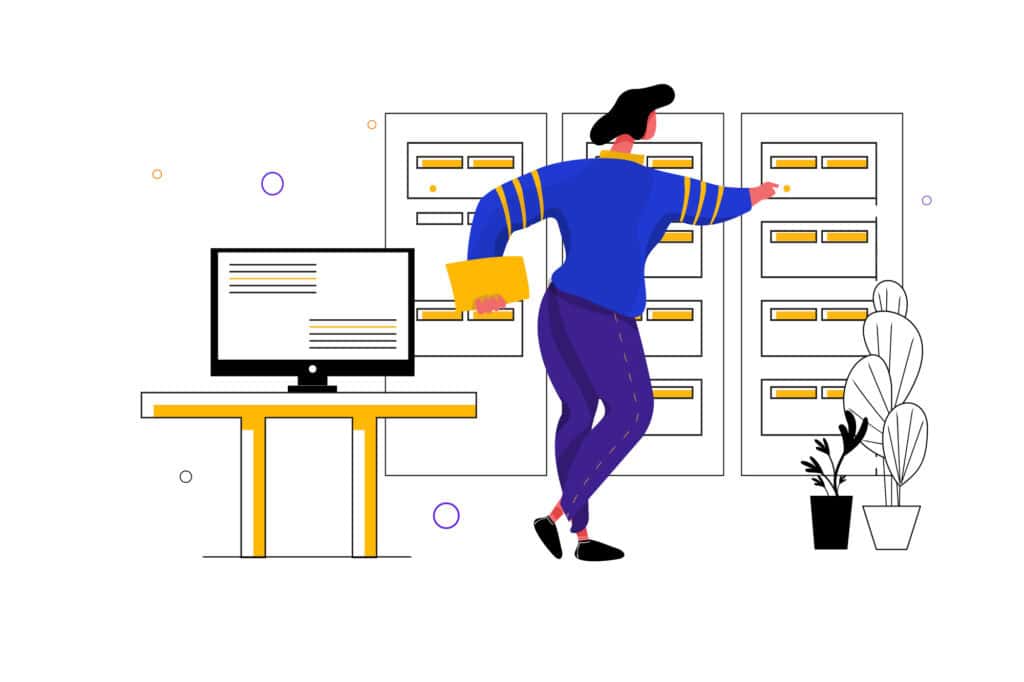
プロジェクトにおけるリスクとは、計画の進行を妨げる要因や、予測できない不確実な事象のことです。リスクが発生すると、スケジュールの遅延、コストの増加、品質の低下といった問題が生じ、プロジェクト全体の成功を脅かす可能性があります。
具体的には、人的リソースの不足、予算オーバー、技術的な障害、関係者間の認識のズレなどが挙げられます。こうしたリスクの影響を最小限に抑えるには、早い段階でリスクを洗い出し、優先順位を決め、適切な対策を講じることが重要です。
リスクの種類

プロジェクトにおけるリスクは、「個別リスク・全体リスク」、「事象リスク・非事象リスク」の二軸に分類できます。それぞれの特徴を把握することで、適切な管理や対策を検討しやすくなります。ここでは、それぞれの違いや注意点について詳しく解説します。
個別リスク・全体リスク
個別リスクとは、リスクが発生した場合にプロジェクトの1つ以上の目標に影響を与えるリスクのことです。たとえば、設備の故障によって業務が滞るリスクや、人的リソース不足などが該当します。
一方、全体リスクとは、プロジェクト全体に影響を及ぼす可能性があるリスクのことを指します。個別リスクやその他の不確実要因が組み合わさることで発生し、スケジュールやコスト、品質などあらゆる面に影響を及ぼす可能性があります。市場の変化や組織方針の転換といった大規模な外部要因も含まれるため、早期の把握が欠かせません。
事象リスクと非事象リスク
事象リスクとは、将来起こるかどうかが不確実な出来事に関連するリスクのことです。たとえば、主要な納入業者の廃業や、設計完了後の顧客からの仕様変更要求などが該当します。
一方、非事象リスクとは、確実に起こるが、結果が変動する可能性があるリスクのことです。非事象リスクは、さらに「変動リスク」と「曖昧さリスク」の2つに分類できます。
変動リスクとは、計画された事象や活動の特性に不確実性があるリスクのことです。たとえば、生産性が目標値を外れる、予測よりも不良品が多いなどの事象が該当します。
曖昧さリスクとは、知識や理解の不足によるリスクのことです。たとえば、法令の解釈があいまいなまま進めてしまい、後に規定違反が判明して大幅な修正が必要になる、といったことが挙げられます。
プロジェクト管理における主なリスク要因

プロジェクトを円滑に進めるためには、あらかじめリスク要因を正確に把握し、早期に対処策を検討することが不可欠です。多くの現場で頻繁に発生しやすいリスクは以下の4つです。
- 明確性の欠如
- リソース不足
- コミュニケーション不足
- 役割の不明確さ
それぞれの内容を見ていきましょう。
明確性の欠如
プロジェクトの目的や範囲、納期が不明確なまま進行すると、関係者間で認識のズレが生じ、スケジュールの遅延や予算超過につながります。特に、クライアントと開発チームの間で要件が曖昧な場合、仕様変更が頻発し、手戻りが増加するため、作業コストが膨らむリスクがあります。
また、要件が適切に文書化されていないと、関係者の解釈が分かれ、実装の方向性が統一されません。結果、大幅な修正が必要になる可能性があります。
このようなリスクを防ぐためには、プロジェクト開始前に要件を明確にし、関係者全員が共通認識を持つことが不可欠です。
リソース不足
プロジェクトには、人材・資金・設備・時間などのリソースが欠かせません。不足すると、スケジュール遅延、コスト増加、品質低下といった問題が発生します。
特に人材不足は、業務の停滞や品質の低下を招き、プロジェクト全体の進行を妨げる要因となります。
リソース不足は、プロジェクトの成功を大きく左右するリスクの一つです。影響を正しく理解し、適切に管理することが求められます。
コミュニケーション不足
プロジェクトを円滑に進めるには、チーム内での情報共有が欠かせません。しかし、コミュニケーション不足により、伝達ミスや認識のズレが生じ、進行に支障をきたすことがあります。
例えば、仕様変更が共有されず手戻りが発生する、タスクの役割が不明確で作業の重複や漏れが起こるといった問題が起こり得ます。
コミュニケーション不足は、プロジェクト全体の管理に関わる重要なリスクです。その影響を理解し、適切に対応することが求められます。
役割の不明確さ
プロジェクト内でメンバーの役割や責任が曖昧だと、タスクの重複や漏れが発生し、進行が滞るリスクが高まります。例えば、同じタスクを複数のメンバーが担当して非効率になったり、逆に誰も担当せずに重要な作業が放置されるかもしれません。
また、責任の所在が不明確だと、問題発生時の対応が後手に回り、プロジェクト全体のパフォーマンスが低下する要因になります。特に、チームの規模が大きくなるほど、役割の明確化が欠かせません。
そのため、プロジェクト開始時に各メンバーの役割や責任を明確に定義し、文書化することが不可欠です。また、定期的な見直しと調整を実施することで、状況の変化に対応しながら、より効率的な運営が可能になります。
プロジェクトにおけるリスク管理とは

リスク管理とは、プロジェクトの目標達成を阻害するリスクを特定・分析し、適切な対策を講じるプロセスです。スケジュール遅延や予算超過、技術的トラブル、人材不足など、想定外の問題は常に発生する可能性があります。
そのため、リスクの発生確率と影響度を見極め、回避策や緊急対応を事前に計画することが重要です。さらに、定期的なモニタリングとレビューにより、状況の変化に応じた柔軟な対策を講じることが求められます。
適切なリスク管理を行うことで、影響を最小限に抑え、プロジェクトの安定した進行が可能になります。
リスク管理と危機管理の違い
リスク管理と混同されやすいのが危機管理です。
リスク管理は、リスクが発生する前に予防策を講じ、影響を最小限に抑えることが目的です。例えば、スケジュールの遅延リスクを想定し、事前にリソースを確保したり、代替案を用意することが該当します。
一方、危機管理は、すでに発生したトラブルや事故に対処し、被害を抑え、早期に状況を収束させることを指します。たとえば、システム障害が発生した際に、迅速な復旧作業や影響範囲の特定を行うことが危機管理にあたります。
つまり、リスク管理は「予防」、危機管理は「対処」が目的という点が大きな違いです。どちらもプロジェクトの安定運営には欠かせません。
リスク管理とリスクアセスメントの違い
リスクアセスメントとは、リスクの特定・分析・評価を行うプロセスを指します。一方、リスク管理は、これに対策の実施やモニタリングを加えた広範な活動を指します。
つまり、リスクアセスメントはリスク管理の一部であり、リスク管理の中に含まれる活動の一つとして位置づけられます。
リスク管理のプロセス
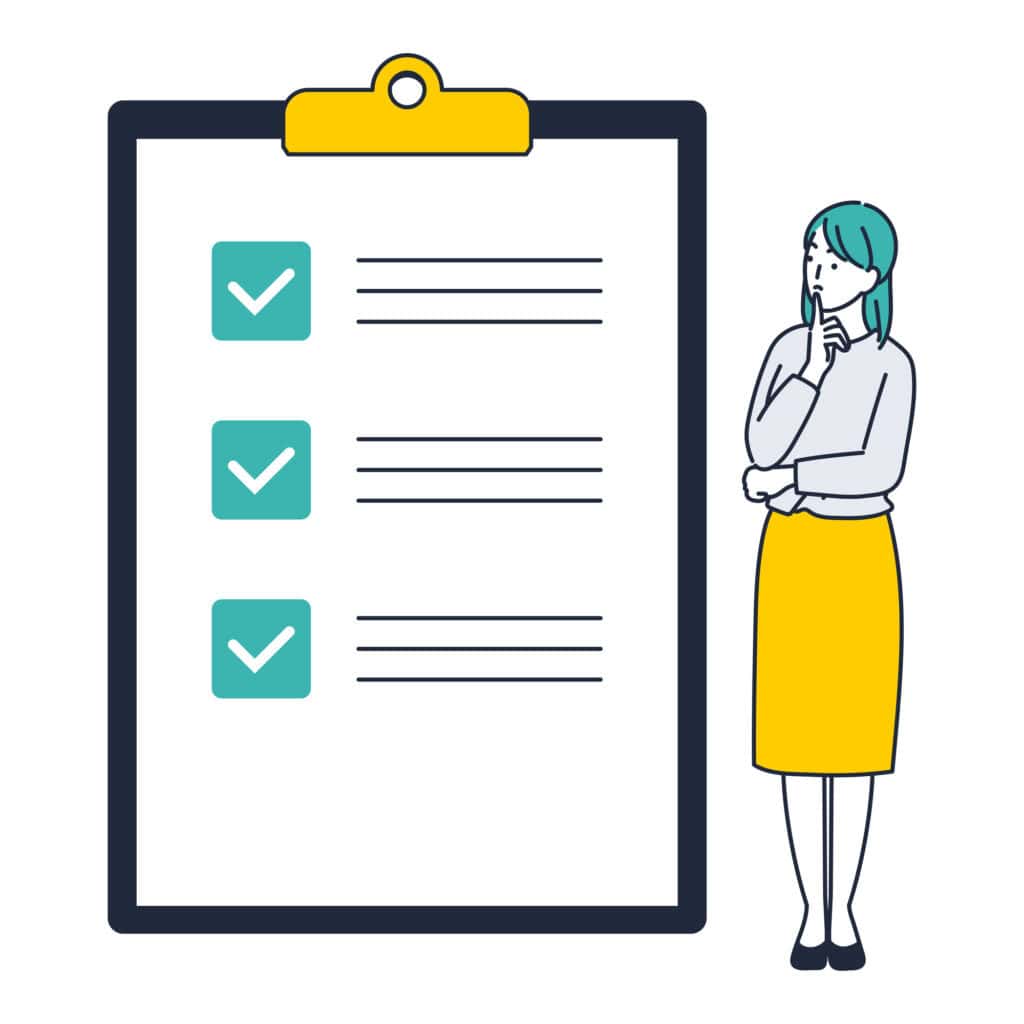
プロジェクトでのリスク管理は、以下のステップで実施するのが一般的です。
- リスクの洗い出し・特定
- リスクの優先度を決める
- 対応策の立案
- 対応策の実施
- 追跡・モニタリング
- 改善
各プロセスのポイントを解説します。
1.リスクの洗い出し・特定
まず、プロジェクトに影響を与えそうなリスクを可能な限り洗いだしましょう。
過去のプロジェクト事例や業界のベストプラクティス、ステークホルダー(顧客・上司・他部署)の意見を参考にしながら、作業面・技術面・外部環境などを幅広くチェックします。
また、チームメンバーの経験則を活用することで、既存データだけでは見えないリスクを補完できます。
2.リスクの優先度を決める
リストアップしたリスクは、発生確率と影響度の両面から評価し、対応の優先度を決定します。
例えば、発生確率が低くても重大な損失につながるリスクは、早期に回避策を検討する必要があります。一方、発生確率が高くても影響が軽微なリスクは、他の重要項目とバランスを取って対応します。
評価結果を「リスク管理表」にまとめて可視化し、チームで共有することで、意思決定をスムーズに進められます。
3.対応策の立案
優先度が定まったら、それぞれのリスクに対する具体的な対応策を検討します。対応策には大きく4つの種類があります。
- 回避:リスク原因を除去し、発生しないようにする。
- 軽減:発生確率や影響度を可能な限り低減する。
- 移転:保険や外注でリスクを他者に移す。
- 受容:コスト対効果を考慮し、あえて対応しない。
どの対応策を選択するかは、プロジェクトの目的や制約条件、想定されるコストを総合的に判断して決めることが重要です。
4.対応策の実施
策定した計画をもとに、リスクに対応します。ここでは、誰が責任を持って行うのか(リスクオーナー)を明確にしておきましょう。担当者が曖昧だと、タスクが放置されたり、統率の取れていない非効率な作業になったりしてしまいます。
また、プロジェクト管理ツール上でタスクを登録し、進捗や残作業を全メンバーが共有できるようにしておくと、抜け漏れや重複を防ぎやすくなります。
5.追跡・モニタリング
対応策を実施した後でも、リスクが完全に解消されるとは限りません。状況が変われば、リスクの内容も発生確率や影響度も変化しうるため、継続的なモニタリングが必須です。たとえば、重要な取引先が経営難に陥った場合は、それに応じて新たなリスクや対策が生まれる可能性があります。
定期的にリスクレビューの機会を設けることで、状況の変化に素早く対応できます。
6.改善
リスク対応策を実施した後は、その効果を振り返り、改善点を洗い出すことが重要です。対応が適切だったか、より効果的な方法があったかを検討し、チーム内で共有します。
例えば、対応策の実施に時間がかかりすぎた場合は、意思決定プロセスやリソース配分を見直すことで、次回の対応を迅速化できます。また、未然に防げた可能性があるリスクについては、事前の対策強化を検討することで、将来的なリスク低減につながります。
こうした改善プロセスを継続的に実施することで、リスク管理の精度が向上し、組織全体の対応力が強化されます。
プロジェクトのリスク管理でBacklogがおすすめの理由

プロジェクトのリスク管理を成功させるには、進捗状況の可視化と、チーム間の円滑な連携が欠かせません。適切な情報共有ができていないと、リスクの発見が遅れ、対応の遅延につながる可能性があります。
Backlogは、ガントチャートやコメント機能など、プロジェクト管理に必要な機能を備えたツールです。これにより、リスクを早期に察知し、適切な対応を迅速に行うことができます。
特に、以下の点で大きな強みがあります。
- プロジェクト進捗のリアルタイムな可視化
- チーム間の円滑なコミュニケーション
- ファイル共有とドキュメント管理
- 適切な権限を付与してセキュリティを高められる
それぞれの特長について解説します。
プロジェクト進捗のリアルタイムな可視化
プロジェクトの進捗をリアルタイムで把握できれば、リスクを早期に検知し、迅速に対応できます。Backlogには、以下のような進捗管理機能が備わっています。
- ガントチャート:タスクの開始日や期限をひと目で把握し、全体のスケジュールを管理。
- ボード機能:タスクカードをドラッグ&ドロップで動かすだけで、タスクの状態を柔軟に変更。
- バーンダウンチャート:マイルストーンごとにプロジェクト全体の進捗を可視化し、遅延を早期に発見。
これらの機能を組み合わせることで、プロジェクト全体の流れと各タスクの状況をリアルタイムにチェックでき、発生しそうなリスクを早めに発見しやすくなります。
チーム間の円滑なコミュニケーション
リスク管理の要となるのは、早期発見と早期対応です。そのためには、チーム内の円滑なコミュニケーションが欠かせません。Backlogでは、コミュニケーションをサポートする様々な機能が搭載されています。
- コメント機能:タスク別に議論を集約し、情報の散逸を防止
- 通知・お知らせ機能:課題の追加・更新を関係者に通知し抜け漏れを防止
- 外部チャット連携:TeamsやSlackなどと連携し、リアルタイムで情報をキャッチ
さらに、チーム全員のタスク量や進捗が可視化されることで、ボトルネックの早期発見が可能になります。例えば、特定のメンバーに業務が偏っている場合や、あるタスクが停滞している場合も、ボード機能やガントチャートで状況をすぐに把握できます。
問題が発生しそうなポイントをチーム全体で共有し、未然に対応できる環境を整えられるのが、Backlogの大きな強みです。
ファイル共有とドキュメント管理
Backlogでは、プロジェクト単位でファイルをまとめられる「ファイル共有」機能や、Wiki機能を用いてナレッジを蓄積できます。
これらを活用すれば、古いデータを参照してリスクを見落とすことや、最新版のドキュメントが見つからず対策が遅れる事態を防げます。また、外出先やリモートワーク時でも、ブラウザやモバイルアプリから常に最新の情報にアクセス可能です。
適切な権限を付与してセキュリティを高められる
セキュリティ対策の不備は、プロジェクト進行にも大きく影響するリスクとなり得ます。Backlogは外部からの不正アクセスや情報漏洩のリスクを防止するために、様々な対策を実施しています。
- 通信はすべてSSL暗号化
- 不正なアクセスはしっかりブロック
- サーバの監視・障害対応
- 毎日1回、データ領域のバックアップ
加えて、ユーザーは独自に以下のような設定も可能です。
- 認証アプリ、SMS、セキュリティキーなどを利用した2段階認証
- 指定したIPアドレス以外のアクセスを制限
- プロジェクトやファイルごとの細やかな権限設定
関連機能:2段階認証 | 機能 | Backlog
プロジェクトの進行に影響を及ぼすセキュリティトラブルを回避し、安心して業務に集中できる環境を整えることが可能です。
また、Backlogのスタンダードプラン以上では、メンバー数による料金の変動がありません。そのため、一時的に他部署や外部の監査機関、弁護士などを招待する際にもコストを気にせず柔軟に対応できます。この点は、特に情報共有や監査を行う際の大きな利点となるでしょう。
最適なツールを活用して、プロジェクトのリスクに対処しよう!

プロジェクトのリスク管理は、スケジュールやコストを守りながら品質を維持するために不可欠です。リスクを早期に特定し、優先度をつけて適切な対策を講じることで、想定外のトラブルを大幅に減らすことができます。
プロジェクトは計画通りに進むとは限らず、スケジュール遅延や予算超過といったリスクが発生することもあります。そのため、リスクの洗い出し・発生確率や影響の分析・具体的な回避策の策定を徹底することで、リスクの影響を最小限に抑え、成功率を高めることが重要です。
プロジェクト管理ツール「Backlog」は、プロジェクトの進捗管理や情報共有をはじめ、リスク管理に欠かせない機能を網羅しているクラウドサービスです。チーム内のタスクを一元的に把握し、コミュニケーションロスや情報の散逸を防ぐことで、リスクの早期発見・早期対応をサポートします。
<Backlogの機能一覧表>
| 機能 | 特徴 |
| ガントチャート | 各タスクやプロジェクト全体の進捗を可視化。ドラッグ&ドロップで簡単にスケジュールを修正。 |
| ボード | プロジェクト内の課題の進捗を一覧で表示。ドラッグ&ドロップでタスクの進捗を素早く更新。 |
| ファイル共有 | プロジェクトごとのファイルを一元管理。関連する課題ページやWikiにリンクを設置することで、簡単にアクセスできる。 |
| Wiki | 議事録や業務フローなど、プロジェクトに関するナレッジを集約。メンバーが自由に追加・編集可能。 |
| バーンダウンチャート | プロジェクトの進捗をマイルストーンごとにグラフで表示。タスクの遅延を瞬時に把握。 |
| 親子課題 | 依存関係にあるタスクを親子課題としてまとめて管理。 |
| 課題ごとのコメント | タスクごとに円滑なコミュニケーションを促進。 |
| お知らせ機能 | プロジェクトに関する更新情報をメンバーに通知。 |
| モバイルアプリ | スマートフォンからタスク管理が可能。プロジェクトの進捗確認のほか、コメント返信やWikiにも対応。 |
Backlogを体験していただくために、30日間の無料トライアル期間を設けています。こちらをお試しいただくことで、実際にBacklogを操作した上で導入をご検討いただけます。
さらに、Backlogの特長や機能、料金プラン、実際の業務改善事例を網羅した資料をご用意しました。以下のリンクから資料をダウンロードいただけますので、ぜひご覧ください。
こちらもオススメ:
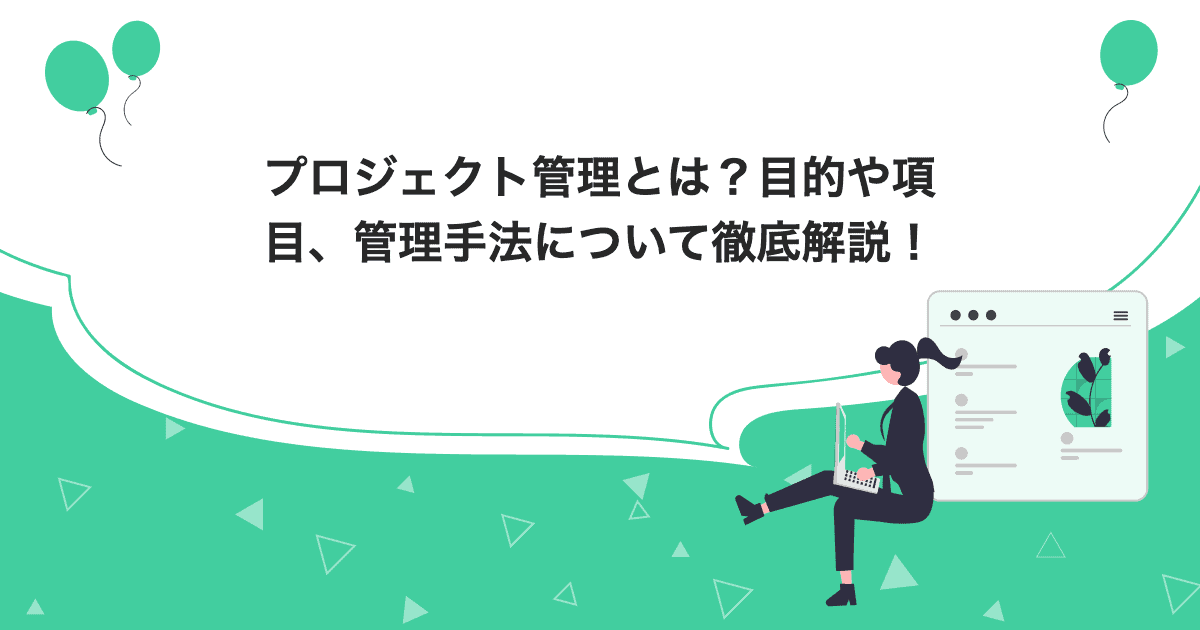
プロジェクト管理とは?目的や項目、管理手法について徹底解説! | Backlogブログ
プロジェクト管理の基本や主な項目を紹介。CCPMやWBSなどのプロジェクト管理の代表的な手法やプロジェクト管理全体の流れを解説。これからプロ…
backlog.com