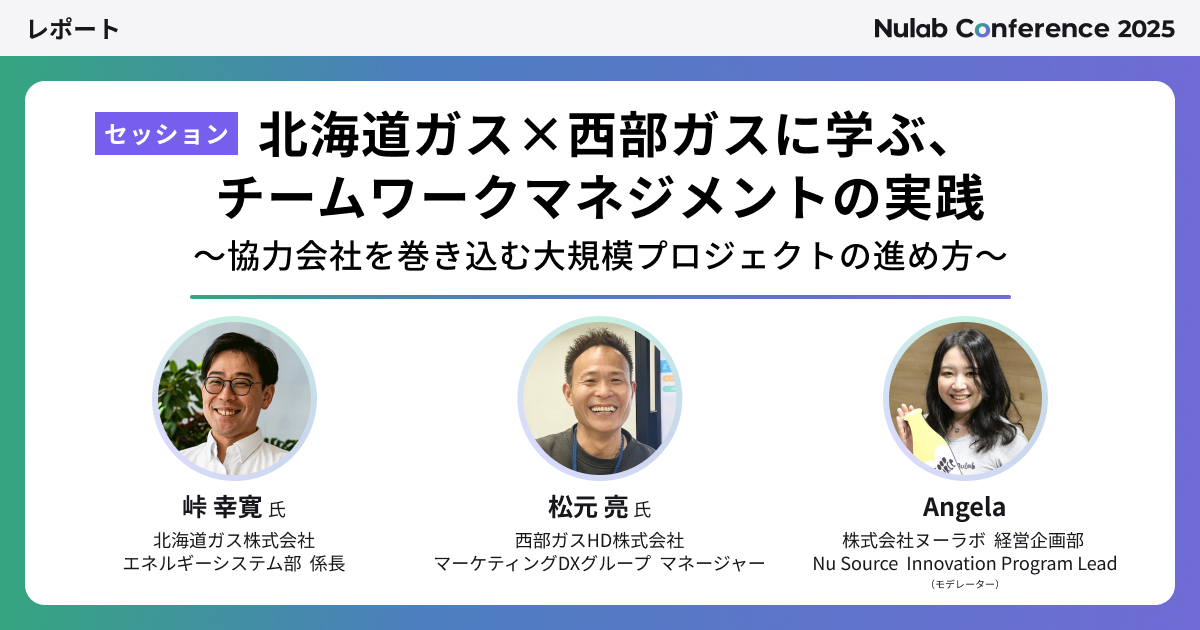
2025年10月17日、品川インターシティホールにて「Nulab Conference 2025 ~ DESIGN YOUR TEAMWORK ~」を開催いたしました。
本記事では、北海道ガスと西部ガス、地域インフラを支える大手企業のお二人をお招きしたセッションをレポートします。Backlog導入の経緯と協力会社を巻き込むアプローチ、そしてプロジェクト推進の工夫を語っていただきました。
なお、本セッションは動画でも公開しております。ぜひご覧ください!
目次
登壇者紹介
北海道ガス株式会社
DX・構造改革推進部 エバンジェリスト
峠 幸寛 氏
西部ガスホールディングス株式会社
マーケティングDXグループ マネージャー
松元 亮 氏
株式会社ヌーラボ
Angela(モデレーター)
ガスの自由化をきっかけに、マーケティング施策が急務に
今回は、北海道と九州を拠点とするガス会社で活躍されるお二人にご登壇いただき、地域インフラを支える企業の“協働力”に迫りました。
―― お二人は大手企業に勤めながら、DXや業務改革を進めていらっしゃいます。本日は、現場での推進力やチームワークマネジメントの実践、プロジェクトの裏側や工夫についてお伺いしたいと思います!それでは、簡単に自己紹介をお願いします。(Angela、以下省略)
峠氏(以下、敬称略):北海道ガスはその名の通り、北海道で100年以上続く歴史のあるガス会社です。僕自身は、ガス業界にいながら発電所の設計をはじめ、多様な業務に携わっていました。現在はDX推進部で20年以上使っていた基幹システムの刷新に向けたプロジェクトマネジメントを行っています。
 北海道ガス株式会社
北海道ガス株式会社
エネルギーシステム部
係長
峠 幸寛 氏
松元氏(以下、敬称略):西部ガスホールディングス(以下、西部ガス)は、九州を拠点とする、同じく100年近く続く企業です。私は長年ガスを作る側でしたが、2017年のガスの小売全面自由化を機にマーケティング部門へ異動となりました。
―― さっそくですが、Backlog導入前に感じられていた課題や背景を教えてください。
松元:ガス業界はずっと競争がありませんでした。これまでは各地域の都市ガス会社の独占状態で、なにもしなくてもお客さんが入ってきた。ところが、エネルギー自由化によってガスの全面自由化が進められ、一気にお客さんが減ってしまったんです。ちなみに、北海道ガスさんと当社のように、そもそもエリアが分かれている場合は競争は発生しません。
―― 競合企業とお客さんを取り合う必要が出てきたんですね。
松元:たとえるならば「筋肉質のトラ」である電力会社と、規模も小さく「太ったネコ」である当社との闘いです。さまざまな施策を足早に複数打っていく必要があるなか、やり取りはメールや電話……これは現実的ではありませんでした。
―― 外部のパートナー企業さんとのやり取りも発生したとお聞きしました。
松元:マーケティングが急務となり、私も含めメンバーが集められたのですが、マーケティング経験がないメンバーばかり。そこで、外部のパートナー企業と組んで施策を進めることになりました。ところが、結局やり取りはメールや電話。誰が何をやっているのかもわからず、複数のプロジェクトを進めることは困難でした。
 西部ガスホールディングス株式会社
西部ガスホールディングス株式会社
マーケティングDXグループ
マネージャー
―― 峠さんはいかがですか?
峠:「基幹システムの刷新」という、かなり大きな開発プロジェクトだったこともあり、複数のベンダーと社内4~5部門が集まるチームでした。関わるメンバーも多いので、そのやり取りや質疑をエクセルに落としていくと、500行くらいになってしまったんです。
別の行に同じ質問があって、それぞれ別の回答内容が書かれているなど、「誰が、いつ、どこで、なにを決めたのか」が不明瞭でした。分散された情報をかき集める作業に時間がとられてしまうので、この時間が実にもったいないな、と。
―― 意思決定に関わるログを残すことも大切ですよね。
峠:議事録もワードで管理されていて、各ベンダーの合意確認だけで1週間が経ってしまうような状態。メールに添付されたエクセルやワードのバージョンが錯綜し、どれが最新バージョンなのか管理するのが困難でした。
―― 松元さんもエクセル管理はされていましたか?
松元:エクセルとメールの悩み、共感です。オンラインでの同時編集ではなく、ファイル名でバージョン管理をして、メールに添付して共有していましたね。
峠:ファイル名に「Ver.1」「Ver.2」「最新版」「最新版-2」のような…… 双方が同時に「最新版」を更新し、その内容をマージしたり、作業工数ばかりかかっていましたね。
―― なるほど、よくわかります。こういったお悩みを抱えている企業さんはまだまだ多そうです。
 株式会社ヌーラボ
株式会社ヌーラボ
経営企画部
Nu Source Innovation Program Lead
Angela
決め手は直感的な使いやすさと、メンバーが増えても質を担保できる料金体系
―― お二人とも、メールやエクセルによる管理に苦労されていたんですね。ではここからは、どうしてBacklogを選んだのか?また、導入にあたってのハードルや工夫した点などをお聞きしましょう。
峠:通常だとセキュリティチェックだけで数か月を要することもありますが、北海道ガスではもともとBacklogを使用していた部門があり、利用開始まではスムーズでした。
―― 導入の決め手は何ですか?
峠:“国内製のSaaSである”という点と、ユーザー課金ではなくて“スペース課金である”の二点が大きな決め手でした。どれだけ関わるメンバーが増えても同じ粒度で管理できるので、これが最大の強み。「どうやって社内申請を通したんですか?」という相談をいただくのですが、この話をよくしています。コストメリット・スケールメリットの両方があるんです。
―― なるほど。もし人数課金だとしたら、それぞれの利用人数を計算したり、増えたら再申請したりする必要も出てきますね。
峠:そうですね。見られる人数が限られてしまうのは、スピード感をもって進めたいプロジェクトにとっては大きな痛手です。セキュリティも問題ないし、「だからBacklogでやろうよ」というのが自然に決まりましたね。
―― 松元さんはいかがですか?
松元:パートナー企業のBacklogスペースに、ゲストユーザーとして招待されたことが出会いです。直感的な使いやすさやコミュニケーションのしやすさ、誰がどの作業を担当しているかがわかりやすい点に一目惚れして、すぐに自社でも導入したいと思いました。
ただ、そのときはまだクラウドに否定的な時代で、情報セキュリティ部門に断られてしまったんです。そこで、当時所属していた営業部門側でルールを決めて責任を持って運用することを条件に、半ば強引に導入を進めていきました。
―― 導入までのご苦労があったんですね。現在はそんな情報システム部門の方もBacklogを使っていると聞いて安心しました!導入後の社内浸透ではいかがでしたか?
松元:ありがたいことにパートナー企業の理解があり、どの会社もBacklogでのやり取りに賛同してくれています。新たなパートナー企業を選定する際は「Backlogを使ってプロジェクトをやり取りする」ことを前提にしています。

ルールはとにかくシンプルに。ドキュメント機能で管理者のニーズも満たす
―― 具体的な活用方法やBacklogの運用ルールについて伺いたいと思います。峠さん、いかがですか?
峠:Backlogの一番の魅力は、オンライン空間上の情報をきれいに整理整頓できるところだと考えています。僕の中では「デジタル図書館」のようなもの。ある本棚にプロジェクトの情報を全部入れておき、その本棚の前に立って作業し、終わったら返すというイメージです。「本棚を整理していくことが、みんなの作業効率につながる」というコンセプトを持って運用しています。
―― 「デジタル図書館」ですか!
峠:図書館って、「カテゴリー」「著者名」「タイトル」というシンプルなルールで管理されていますよね。そういうシンプルなルールにしないと、みんなが徹底できないんです。Backlogも同じで、ルールはとにかくシンプルにすることが大切です。課題を作成する際は、「目的」「作業内容」「資料」を必ず入れることを徹底しています。常にきれいにしておけば、きれいな本棚を保てるんです。
―― なるほど。整理しておけば、必要な情報をすぐ取り出せますね。こういったプロジェクト管理ツールでは、管理者(上司)がなかなか見てくれないというお悩みも聞きます。
峠:現場担当者と管理者とでは、欲しい情報が違うんですよ。そこで、僕は「ドキュメント機能」を活用しました。ドキュメント機能に管理者用のページを作り、チームの作業状況をまとめて記載しています。Backlogは検索フィルターの情報もURLに組み込まれているので、フィルタリングした結果のURLをチームごとに貼っておけばよい。上司は、ワンクリックで自分が見たい本棚の前にすぐに立てる。知りたい情報がすぐ取り出せるんです。

―― ワンクリックで見たい本棚の間に立てる……名言ですね!西部ガスさんではいかがですか?
松元:当社の場合は、やることを二つだけ決めて運用しています。「すべてのコミュニケーションはBacklogで行う」こと、そして「課題を登録して自分が返したら、次の担当者を必ず設定する」こと。
このルールを徹底することで、課題一覧を見れば担当者が誰かがひと目でわかり、同時にプロジェクトがどこで停滞しているかわかりやすくなります。自分が担当になったままだとちょっと嫌なので、早く次に回していくという意識がメンバーに浸透しました。
―― 課題の標準化や整理という点で、工夫されていることはありますか?
松元:ナレッジは「Wiki」にまとめるようにしているので、新しいメンバーがきても、Wikiを見れば内容を把握できるように整備しています。私は整理整頓があまり得意ではないのですが、最近は「Backlog AIアシスタント」にすっかり助けられています。モニターで使用しているのですが、「こういった課題はどこにある?」とチャットで聞くと、課題キーとともに概要が表示されるので非常に便利なんです。
―― 「Backlog AIアシスタント」、便利ですよね!本日のセッションでもご紹介していますので、ぜひ覗いてみてくださいね。
Backlogがもたらした変化。オープンでフラットなチームに
―― Backlogの導入から活用、推進まで担っているお二人ですが、Backlogによってチームにどのような変化が起きたと感じていらっしゃいますか。
松元:Backlogは個人チャットができないので、すべての情報がフラットかつオープンに公開されます。情報をオープンにすることで、隠しごとなくチーム全体で「目標」に向かうことができるんです。さらに、チームメンバー全員と情報をシェアしながら進められるという「心理的安全性」が生まれたと感じています。
―― チームワークマネジメントでいう、「目的の共有」と「心理的安全性」が実現できている状態ですね。
松元:大企業からフリーランスまで、異なる所属のメンバーが情報を共有しながらプロジェクトを進めています。誰かが困っていたら「横から失礼します」と助け合える動きにもつながっているんです。

―― チームの皆さんの関係性までつながっているのは、嬉しいですね。峠さんはいかがですか?
峠:情報共有のための打ち合わせが不要になりましたね。これまで情報共有だけだった会議が、より深い議論や判断をする場になり、みんなの作業効率が向上しました。オンライン上の情報の透明性を上げていけば、“これは何のためにやっているのか”、“今どうなっているのか”を共通認識として持てるようになります。こうすることで、みんなが納得感を持ってすぐに作業に移れるようになったんです。
―― お話を伺っていると「コミュニケーション設計」を徹底されたことが、チームワークマネジメントの実現につながったのかなと聞いておりました。
峠:とはいえ、社内にBacklogを浸透させるためには工夫が必要でした。そんなときに活用したのが、外部のコミュニティです。2年前に登壇した「Backlog World 2023」の動画が外部で評価され、社内で閲覧する人が増え、逆に「これはどうやったら使えますか」という相談がくるようになったんです。
―― お二人のような強いリーダーが推進してくださったことも大きいですね。先ほどコミュニティという言葉も出てきましたが、Backlogユーザーコミュニティ「JBUG」では、全国のユーザーさんがBacklogの使い方やノウハウを共有し合っています。気になった方はぜひ、そういった場に一歩足を踏み出してみるといいかもしれませんね。
未来のチームをよくするために、これからチームワークマネジメントに取り組む方へ
―― それでは最後に、これから「自分のチームをよくしていこう」と頑張っていらっしゃる皆さんへ、明日からできることをアドバイスいただけると嬉しいです!
松元:まずは、自分のチームだけでもBacklogを導入して使ってみることをおすすめします。チームリーダーの方は、メンバーの発言が徐々に洗練されていくことが実感できると思うんです。新入社員が入ってきて使い始めると、徐々に専門用語を使いながら適切な指示をパートナー企業に出せるようになっていきます。ぜひ一度使ってみてください。
峠:自分で使ってみて、自分の“本棚”がきれいになっているか、確認することが大切です。自分の作業が楽になってきたら、3名程度の小さなチームで始めるのが良いと思います。どういう視点で管理するときれいな本棚が作れるかを小規模で試してみて、一緒に作業するという経験が重要です。整理整頓をしてきれいにすることは当たり前ですが、「Backlog上でそれを実践すると、時間がかからないんだ」という体験をしてもらい、それを徐々に広げていくことが大事だと思います。
―― まずはスモールスタート、がポイントですね!
峠:今日のお話は、10月2日に発売したBacklog初の公式ガイドブック「ゼロからはじめるBacklog活用大全」の118ページにも掲載されていますので、ぜひ読んでみてください!
―― 最後に宣伝もありがとうございます!Backlogを体験すること、そしてそれを共有するという最初の一歩の重要さが分かったお二人のセッションでした。11月29日には「Backlog World 2025」も開催されますので、もっとお話が聞きたい方はぜひお越しください。峠さん、松元さん、ありがとうございました!
Nulab Conference 2025レポート
Nulab Conference 2025のテーマは「チームワークマネジメント」。経営・現場・研究、それぞれの立場から、組織づくりのヒントと次の時代の“チームのかたち”について白熱したディスカッションが行われました。
そのほかのセッションレポートもぜひご覧ください。

Nulab Conference 2025 レポート:【基調講演】「次の時代をつくる、チームのかたち」── 国産SaaSリーダーが語る、これからの組織とチームワーク | Backlogブログ
2025年10月17日、品川インターシティホールにてNulab Conference 2025を開催しました。サイボウズ青野氏、さくらインタ…
backlog.com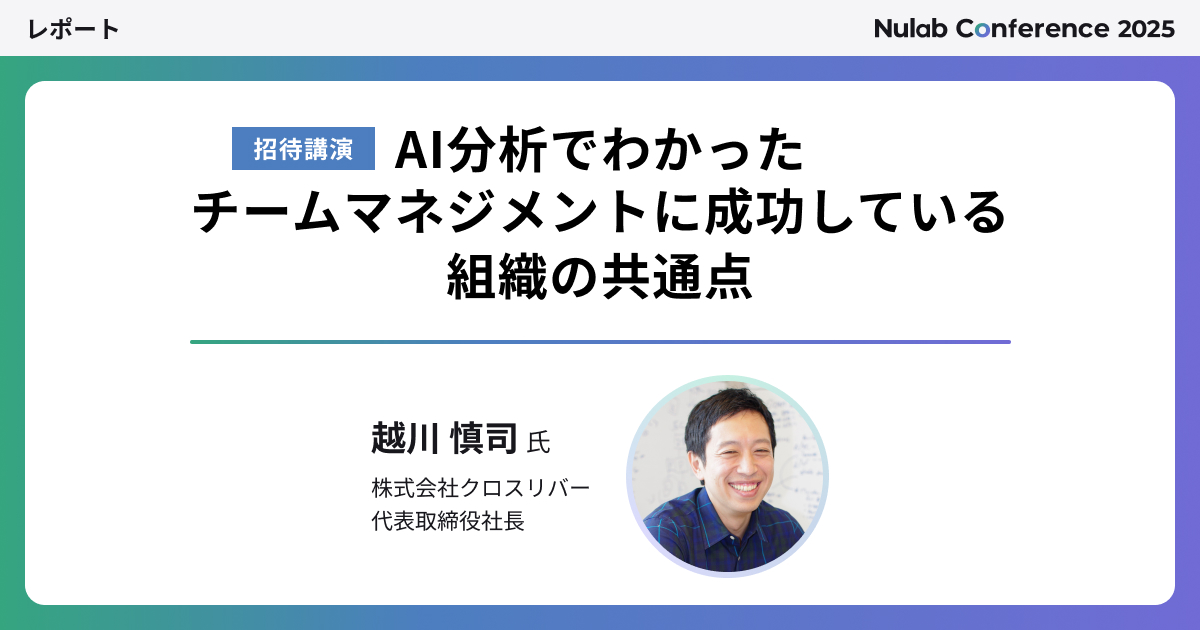
Nulab Conference 2025 レポート:AI分析でわかったチームマネジメントに成功している組織の共通点|越川慎司氏 招待講演 | Backlogブログ
10月17日に開催された、「Nulab Conference 2025」。クロスリバーの越川氏にご登壇いただいた招待講演のレポートを公開!あ…
backlog.com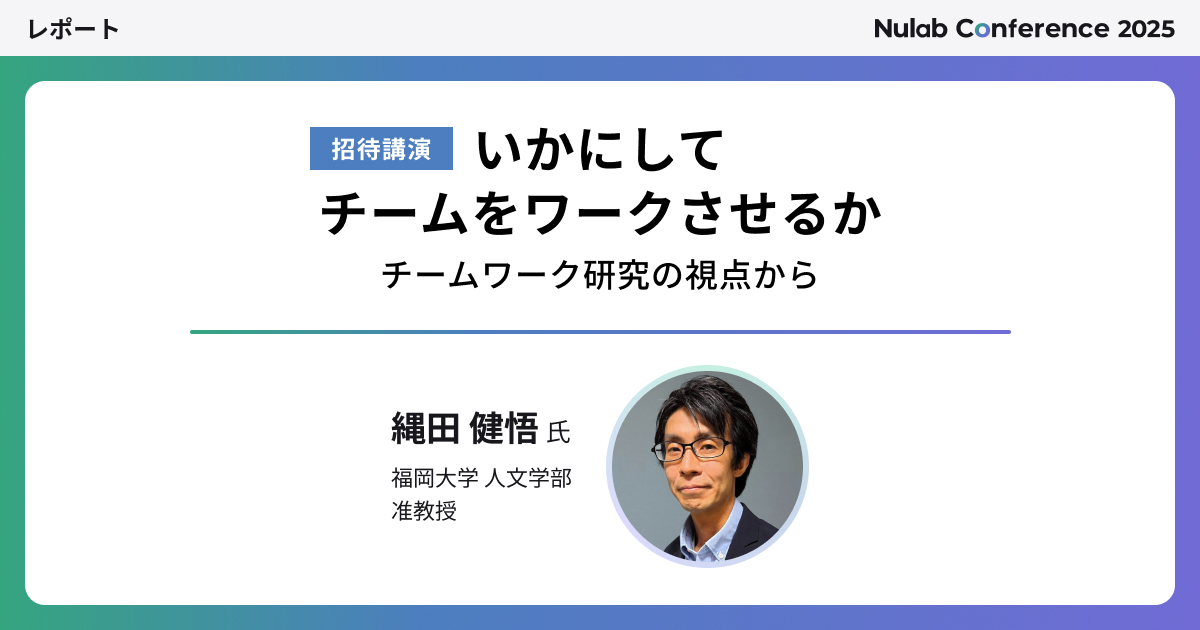
Nulab Conference 2025 レポート:「いかにしてチームをワークさせるか」── チームワーク研究の視点から|縄田健悟氏 招待講演 | Backlogブログ
10月17日に開催されたNulab Conference 2025。福岡大学 縄田氏の招待講演をレポート!心理的安全性、4階建てのチーム構造…
backlog.com
Nulab Conference 2025 レポート:進化を続ける成長企業のチーム戦略 ── 実例でひも解くチームワークマネジメント | Backlogブログ
10月17日に開催された「Nulab Conference 2025」。急成長を遂げたデジタルキューブ、HACARUS、2社の代表によるパネ…
backlog.com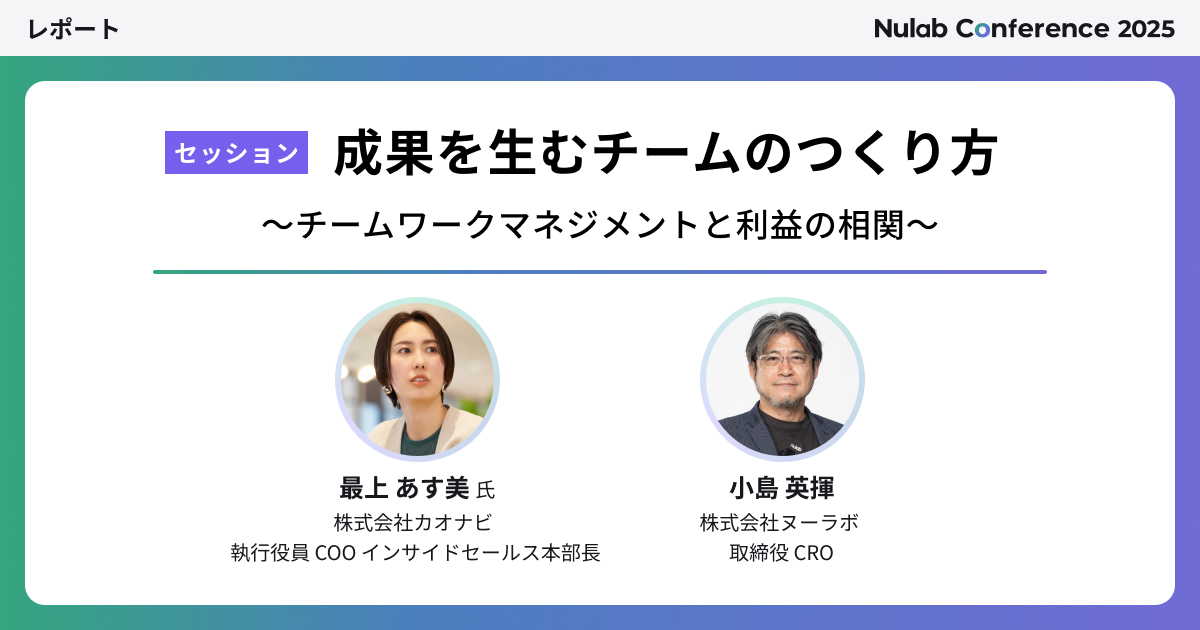
Nulab Conference 2025 レポート:成果を生むチームのつくり方 ── チームワークマネジメントと利益の相関 | Backlogブログ
10月17日に開催された「Nulab Conference 2025」。「成果を生むチームのつくり方」と題し、カオナビCOO最上あす美氏と、…
backlog.com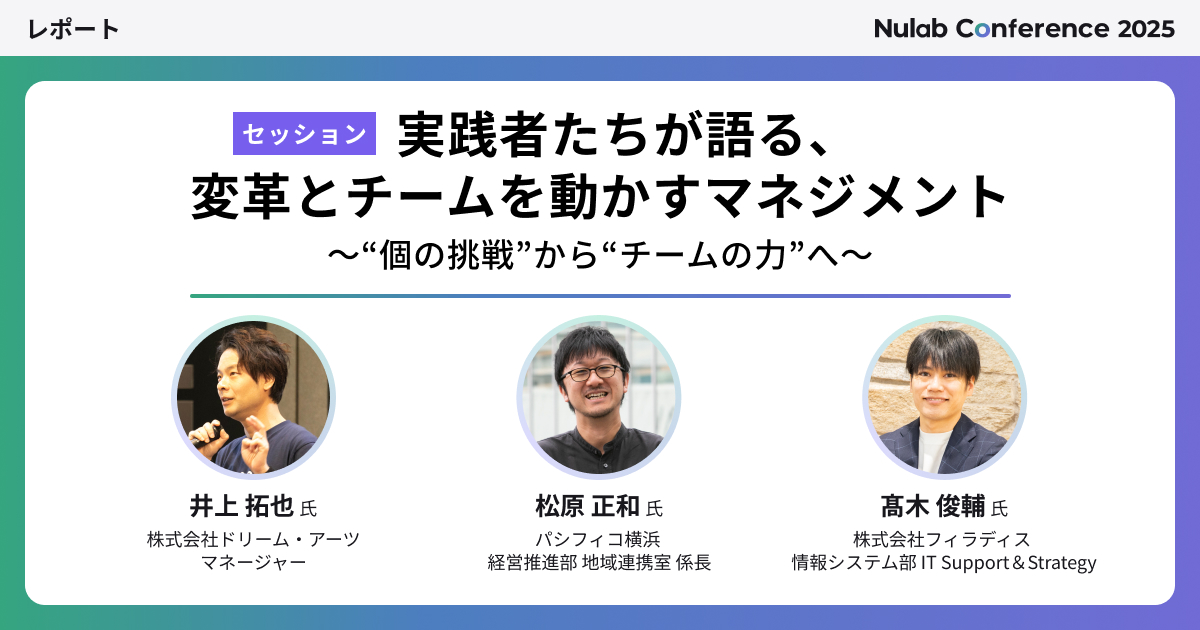
Nulab Conference 2025 レポート:実践者たちが語る、変革とチームを動かすマネジメント 〜“個の挑戦”から“チームの力”へ〜 | Backlogブログ
10月17日に開催された「Nulab Conference 2025」。Bステージのユーザーセッションの様子をお届けします!現場で培ったリア…
backlog.com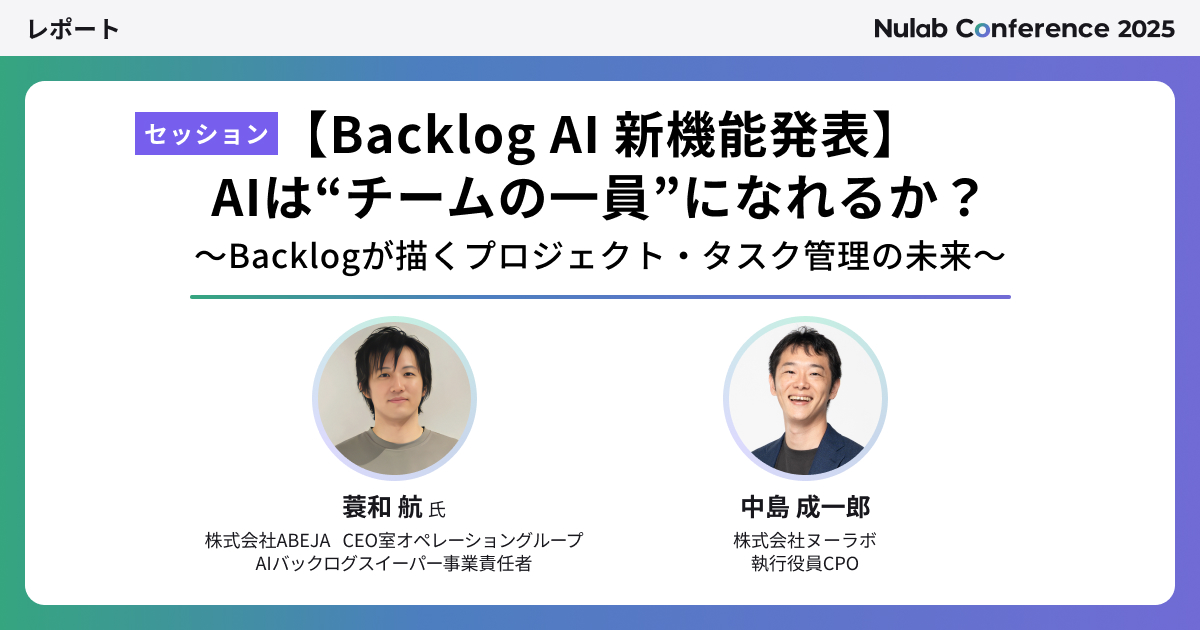
Nulab Conference 2025 レポート:Backlog AI 新機能発表!Backlogが描くプロジェクト・タスク管理の未来 | Backlogブログ
10月17日に開催されたNulab Conference 2025。2026年初頭リリース予定の新機能「Backlog AI アシスタント」…
backlog.com