
チームビルディングとは、メンバーの個性やスキル、能力を最大限に活かし、共通の目標を達成するための取り組みを意味します。これによりチームとしての力を高め、成果の最大化を目指します。
本記事では、チームビルディングの概要や目的、メリット、成功のためのポイントについて解説します。
成果を上げるためには、各メンバーが自律的に動き、円滑に連携できるチーム設計・運営が必要です。こういった環境づくりに役立つのが「チームワークマネジメント」です。
記事の後半では「チームワークマネジメント」を取り上げ、チームの力を最大化し、組織力を高めるポイントを解説します。
オンデマンド配信:「次の時代をつくる、チームのかたち」国産SaaSリーダーが語る、これからの組織とチームワーク
目次
チームビルディングとは

チームビルディングとは、メンバーが持っている能力やスキルを最大限に発揮できる環境を整える取り組みのことです。組織開発の手法の一つであり、チームが効率良く目標を達成するために用いられます。
チームビルディングの対象者には、制限がありません。新入社員や内定者、管理職、経営者など、組織に属するすべての人が対象になります。
チームビルディングのチームワークとの違い

チームビルディングと混同しやすい概念が「チームワーク」です。チームワークとは、チームのメンバー同士で弱点を補い合いながら、特定の目標を達成するための行動や意識のことを指します。短期的な特定の課題に対する取り組みとして位置付けられます。
一方、チームビルディングは、メンバーそれぞれの個性やスキルを生かすことを重視しているのが特徴です。中長期的な視点を持った取り組みとして位置付けられます。
両者をバランスよく取り入れることで、より強固で持続可能な組織運営が実現できるようになります。
チームワークを高める方法は「チームワークを高めるために必要なこととは?具体的な方法を紹介! 」をご覧ください。
チームビルディングの主な目的

チームビルディングの主な目的は、以下の5つです。
・組織のビジョンを浸透させる
・心理的安全性を確保する
・共通認識を持ちマインドセットを形成する
・適切な人材配置をおこなう
・チームの生産性を向上させる
どのような目的で実施し、どういった効果を得られるのかを事前に理解しておくことが大切です。それぞれの内容を見ていきましょう。
組織のビジョンを浸透させる
チームビルディングは、新規プロジェクトのキックオフや新しい期の開始など、節目のタイミングで実施されるケースが多く見られます。こうした場で組織のビジョンを共有することで、チーム全体の一体感を高めることが可能です。
さらに、メンバーが共通のビジョンに向かって行動する意識を強化できるため、モチベーションの向上にもつながるでしょう。
チームビルディングによってビジョンが浸透すれば、日常的な意思決定の基準にもなり、長期的に一貫性のある行動を促す効果が期待できます。組織全体が同じ方向を目指して進むことで、持続的な成長につながります。
心理的安全性を確保する
チームビルディングには、心理的安全性を確保するという目的もあります。
心理的安全性が高まると、メンバー同士の交流が増え、コミュニケーションが活発になります。相互理解が深まることで、本音を言いやすい環境が整い、課題や改善点の共有も円滑に進められるでしょう。
さらに、新しいアイデアが生まれやすくなり、イノベーションが活発化します。安心して挑戦できる環境は、組織全体の活力や成長にも直結します。
共通認識を持ちマインドセットを形成する
マインドセットとは、個人が物事をどのように捉え、考えるかを示す価値観や思考の枠組みを意味します。
チームビルディングでは、組織の目標を達成するために必要なマインドを共有し、新たに形成できます。その過程でメンバー間の意識が統一され、方向性のずれを防ぐ効果も見込めるでしょう。
共通のマインドセットが定着すれば、意思決定や行動方針に一貫性が生まれ、チーム全体の動きが揃いやすくなります。その結果、協力体制が強化され、組織全体のパフォーマンス向上につながります。
適切な人材配置をおこなう
チームビルディングを実施することで、メンバー一人ひとりの考え方を把握し、適切な役割分担が可能です。さらに、各メンバーのスキルや経験を理解することで、最適な人材配置をおこなうことも目的の一つです。
メンバーが自分の強みを発揮できるポジションに就くことにより、各人のモチベーションや責任感が高まり、組織全体の成果向上にもつながります。人材配置の最適化は、個人の成長と組織の成長を同時に促す重要な取り組みです。
チームの生産性を向上させる
チームビルディングを実施することで、チームの生産性を向上させる事も可能です。メンバーが互いに信頼し合い、コミュニケーションを深めることで、業務効率が高まります。
作業の重複や無駄も減り、限られたリソースを効果的に活用できるようになることで、チームの生産性向上につながるのです。意見交換が活発になることで、新しい発想や改善策なども生まれやすくなるのも大きなメリットです。
チームビルディングにおける5つのプロセス「タックマンモデル」とは?

チームビルディングのプロセスは、以下の5段階に分類できます。
1.形成期
2.混乱期
3.統一期
4.機能期
5.散会期
これは「タックマンモデル」と呼ばれる代表的なフレームワークです。タックマンモデルは、心理学者ブルース・W・タックマンが提唱した理論であり、チーム形成から解散までの流れを体系的に示しています。
形成期
チームビルディングのプロセスの1つ目の形成期とは、チームの構成メンバーが決まった初期のフェーズのことです。フォーミングとも呼ばれています。この段階ではまだ共通の目標が明確でなく、メンバー同士の理解も浅いため、緊張感が漂いやすいのが特徴です。
形成期では、コミュニケーションの量が特に重視されます。自己紹介や交流の機会を多く設けることで相互理解が進み、メンバー同士の関係を深めることが可能です。
ビジネスにおけるチームビルディングでは、形成期で信頼関係の基盤を形成することで後の成果につながりやすくなります。
混乱期
混乱期はストーミングとも呼ばれ、意見の食い違いや対立が生まれやすいフェーズです。この段階ではチームとしての目標は定まり、プロジェクトも動き始めていますが、価値観や考え方の違いが表面化しやすくなります。
混乱期は、コミュニケーションの質も重要です。チーム全体のモチベーションが下がりやすい時期であるため、リーダーを中心に話し合いの場を設けることが求められます。これにより、相互理解を深めることができるでしょう。
統一期
統一期はノーミングとも呼ばれ、チームが安定状態へ移行するフェーズです。
メンバーの役割分担が明確になり、互いの信頼関係が強まることで団結力が高まります。意思疎通もスムーズになり、チームとしての方向性が固まりつつある段階です。
統一期は、メンバー間で合意した目標を着実に達成することが求められます。安定的に成果を生み出す体制を整えることがポイントです。
機能期
機能期は、チームに強い結束力が見られ、互いにサポートし合う体制が整うフェーズです。
メンバーそれぞれが役割を全うしながら協力することで、チーム全体として高い機能性を発揮します。意思疎通も円滑で、効率的に業務を進められるのが特徴です。
機能期は、高いパフォーマンスを持続的に発揮し、成果を最大化することが求められます。機能期を安定的に維持することで、組織全体の競争力強化に直結するでしょう。
散会期
散会期はアジャーニングとも呼ばれ、プロジェクトの終了でチームが解散するフェーズです。
チームビルディングの成果は、チーム解散時のメンバーの反応によって測ることが可能です。互いを称え合い、解散を惜しむ様子が見られる場合、一連の取り組みが効果的であったと判断できるでしょう。
散会期を前向きな経験として終えることで、メンバーは次のプロジェクトでも高い意欲をもって業務に取り組めます。
チームの成長を加速させる!チームビルディングを高める4つの方法

チームビルディングを高めるには、具体的な方法を理解し、実践することが大切です。代表的な方法としては、以下の4つが挙げられます。
・チームルールを作成する
・1対1で話せる機会を設ける
・研修やセミナーを実施する
・ゲームやアクティビティなどのイベントを実施する
チームルールを作成する
チームビルディングには、メンバーが安心して働ける心理的安全性を確保することが欠かせません。そのための有効な手段の一つが、チームルールの作成です。
たとえば「会議で誰かの意見を頭ごなしに否定しない」「数値に基づいて意思決定する」といったルールを設けると良いでしょう。こうしたルールはメンバーが意見を出しやすい環境を生み、結果としてコミュニケーションの活性化やチームの一体感向上につながります。
また、ルールを定期的に見直し、チームの実情に合った形で機能させることも重要です。
1対1で話せる機会を設ける
定期的な1on1ミーティングの実施も、チームビルディングを進めるうえで非常に有効な手段です。チームには、キャリアや働き方が異なる多様なメンバーが集まるため、オフラインで顔を合わせる機会が限られているケースもあるでしょう。
そのような状況でも、リーダーとメンバーが1対1で直接話す場を設けることは、信頼関係の構築や不安の解消につながります。
1on1ミーティングでは、個々の意見を丁寧にくみ取ることで、風通しの良いチームを作れるでしょう。課題や不満を早期に発見できるため、トラブルを未然に防ぐ効果も期待できます。
研修やセミナーを実施する
研修やセミナー、ワークショップの実施も、チームビルディングの効果を高める有効な方法です。内容は知識やスキルを習得する形式に限らず、楽しみながら取り組めるものや意見交換を重視するものなど、幅広く設定するのが望ましいでしょう。
たとえば、グループディスカッションや体験型ワークを取り入れることで、自然なコミュニケーションが生まれ、メンバー同士の理解も深まります。学びと交流を両立させる研修やセミナーは、チームの結束力を高めるきっかけとなるでしょう。
研修で得た気づきや学びを業務に活かすことで、組織全体の成果向上にもつながります。
ゲームやアクティビティなどのイベントを実施する
大人数でのチームビルディングには、ゲームやアクティビティといったイベントが効果的です。楽しみながら取り組める活動を通じて、メンバー同士の交流が促進され、信頼関係を築きやすくなります。
実施する内容は、タックマンモデルの各段階に応じて選ぶとさらに効果的です。
たとえば、形成期には、メンバーが楽しめることを重視したゲームを取り入れます。これにより、メンバー同士の緊張を和らげることが可能です。
混乱期には、意見を出し合いながら協力するタイプのアクティビティを選ぶと良いでしょう。これにより、相互理解を深めることができます。
【具体例】チームビルディングにおすすめのゲーム・レクリエーション

チームビルディングにおすすめのゲーム・レクリエーションを4つ紹介します。ゲームやレクリエーションを取り入れることで自然なコミュニケ
NASAゲーム
NASAゲームは、チームメンバーが宇宙での生存に必要なアイテムの優先順位を決めるゲームです。まずは個人で考え、その後にグループで意見を出し合いながら答えをまとめます。
NASAゲームの特徴は、メンバーの発想や価値観の違いを体験できる点です。合意形成の重要性や説得力を養えるメリットもあります。
アセンブリーゲーム
アセンブリーゲームは参加者に配られた部品を使い、同じ形や大きさのものを無言で協力しながら組み立てるワークです。言葉を使わずに協力するため、非言語コミュニケーションの重要性を体験できます。
アセンブリーゲームでは、チームでの連携や役割意識の強化が可能です。メンバー同士の信頼関係構築にもつながります。
アイスブレーカー
アイスブレーカーとは、オンラインミーティングや研修の冒頭でおこなわれる軽い自己紹介や質問タイムのことです。
たとえば、好きな食べ物や趣味を共有することで場が和み、参加者がリラックスして発言しやすい雰囲気を作れます。初対面の緊張を和らげ、チームビルディングの円滑なスタートにも役立つでしょう。
コンセンサスゲーム
コンセンサスゲームは、与えられた課題についてグループ全員が納得できる解決策を見つけることを目的としたワークです。個人の意見を持ち寄り、議論を通じて一つの結論を導き出すプロセスを体験できます。
コンセンサスゲームでは、合意形成や協調性を学ぶことが可能です。さらに、メンバー間のコミュニケーションを促進する効果も期待できます。
チームビルディングを成功させる3つのポイント

チームビルディングを成功させるためには、以下の3つのポイントを意識しましょう。
1.チームで達成したい目的を明確に定める
2.メンバーに役割を与える
3.メンバーの適性や相性を考慮したうえでチームを編成する
このポイントを意識することで、チーム力を効果的に高める事が可能です。それぞれの内容を詳しく解説します。
チームで達成したい目的を明確に定める
チームとして達成すべき目的が明確でないと、メンバーはどの業務から始めれば良いか判断できず、活動の方向性が定まらなくなります。そのため、まずはリーダーが中心となってチームの目的を具体的に定めることが重要です。
明確な目的を全員で共有することで、メンバーは同じ方向を向き、効率的に行動できるようになります。メンバーのモチベーションも維持しやすくなるでしょう。目的を具体的に定めることで、チーム全体の一体感が高まり、成果につなげやすくなります。
また、定期的に目的を振り返ることで、必要に応じた改善や軌道修正なども可能です。
メンバーに役割を与える
チームを結成したばかりの初期段階では、メンバー同士が様子を見ながら行動することが多く、主体性が発揮されにくい傾向があります。そこで有効なのが、メンバー一人ひとりに役割を与えることです。
役割が明確になれば、自分の責任を自覚し、主体的に行動できるようになります。また、自分の役割を通じてチームへの貢献を実感できるため、モチベーション向上にもつながるでしょう。
メンバー一人ひとりが与えられた役割を果たすことで、チーム全体の生産性向上にも期待できます。
メンバーの適性や相性を考慮したうえでチームを編成する
チームビルディングでは、メンバーの適性や相性を考慮したうえでチームを編成することが重要です。チームビルディングは、グループワークを好まない人にとっては効果が限定的になるケースもあります。
そのため、各メンバーの能力や性格、価値観を理解したうえでチーム作りを進めることが重要です。適切な編成を実施することで、一人ひとりが力を発揮しやすくなり、チーム全体の成果にもつながります。
メンバーの相性を考慮した編成は、長期的に安定したパフォーマンスを生み出す基盤になるでしょう。
チームビルディングにおけるチームワークマネジメントの重要性

チームビルディングを実施した後は、成果を持続させ、チームを効果的に機能させる仕組みが必要になります。そこで重要となるのが「チームワークマネジメント」です。
チームワークマネジメントとは、異なる職種や部門のメンバーで形成されたチームが共通の目的に向かって自律的に動けるように、チームを設計・運営するための概念を指します。ここでは、チームワークマネジメントが求められている背景や期待できる効果について見ていきましょう。
チームワークマネジメントが求められている背景
少子高齢化やグローバル化、働き方の多様化により、企業は多様なメンバーで柔軟にチームを編成し、成果を上げることが求められています。
しかし、立場や専門性、勤務地が異なるメンバーが連携するのは容易ではありません。コミュニケーション不足や進捗管理の悪化といった課題が生じやすいのが現状です。
こうした課題を解消し、組織の競争力を高めるために必要となるのがチームワークマネジメントです。市場環境の変化が激しい現代においては、迅速かつ柔軟に対応できるチームづくりが欠かせません。効果的なチームワークマネジメントは、持続的な組織成長を支える基盤になるでしょう。
チームワークマネジメントによって期待できる効果
チームワークマネジメントを実践することで、異なるスキルや専門知識を持つメンバー同士の協働が促進され、新しいアイデアやイノベーションが生まれやすくなります。また、業務効率の向上やコスト削減など、ビジネス面でも好影響をもたらすでしょう。
たとえば、部署をまたいだプロジェクトで情報共有の仕組みを整えることで、無駄な作業や重複を減らし、スムーズに意思決定を進められるようになります。その結果、限られたリソースを有効に活用でき、組織全体の成果を最大化できます。
関連記事:チームの力を最大化し、組織の競争力を高める 「チームワークマネジメント」
チームワークマネジメントを成功させるには?よくある課題と解決のヒント

チームビルディングで良好な関係を築いても、実際の業務で連携がうまくいかなければ成果にはつながりません。チームワークマネジメントを成功させるためには、チームが抱えがちな課題を理解し、対策を講じることが重要です。
ここでは、チームワークマネジメントでよくある課題と解決のヒントを紹介します。チームマネジメントに課題を感じている方は、ぜひ参考にしてください。
課題1. 誰が何をしているのか分からず、進捗が不透明
多くのメンバーが関わるプロジェクトでは、「誰が」「何を」「いつまでに実施するのか」が曖昧になりがちです。
タスクの担当者や進捗状況が可視化されていないと、作業の重複や抜け漏れが発生し、プロジェクト全体が遅延する恐れもあります。その結果、納期の遅延や品質低下といった事態につながりかねません。
解決のヒントは、チーム全員のタスクと進捗を一元的に管理し、誰もがリアルタイムで状況を把握できる仕組みを整えることです。たとえば、タスク管理ツールを活用し、担当者・期限・進捗を明確にすれば、無駄を減らしながら効率的にプロジェクトを進められます。
課題2. 情報が点在し、認識のズレや手戻りが発生する
プロジェクトに関する資料や議事録、連絡事項などがチャットツールやメール、個人のPC内に分散していると、必要な情報を探すのに時間がかかります。
また、どの情報が最新か分からなくなり、メンバー間で認識のズレが生じて手戻りの原因にもなるでしょう。その結果、意思決定の遅れや作業効率の低下といった事態に陥りやすくなります。
解決のヒントは、情報を一元管理する仕組みづくりをすることです。たとえば、プロジェクト管理ツールやナレッジ共有ツールを活用し、資料・議事録・連絡事項を集約します。さらに、情報の登録・更新ルールを明確化することも意識してみてください。
課題3. コミュニケーション不足で、チームの連携がうまくいかない
特にリモートワークが普及した現代では、意識的にコミュニケーションの機会を設けないと、メンバー間の連携が希薄になりやすくなります。
業務上の報告・連絡・相談が滞ると、課題の発見が遅れたり、孤立するメンバーが出たりする可能性もあるでしょう。その結果、意思疎通の不備によるミスや生産性の低下につながりやすくなります。
解決のヒントは、タスクや課題に紐づけて気軽にやり取りできるコミュニケーションの場を設け、オープンな情報共有を促進することです。
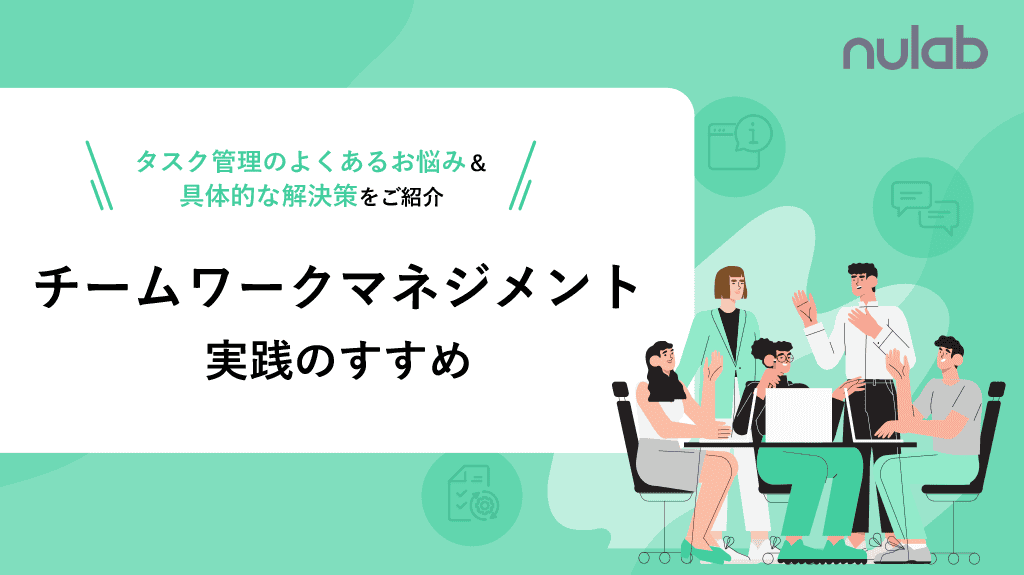
チームワークマネジメントの重要性や課題解決のヒントについて解説しましたが、「具体的に自社のチームでどう実践すれば良いのか」と悩む方も多いのではないでしょうか。
そこで、部門や組織を越えたメンバーがワンチームとなり、効果的に目標を達成するためのチームワークマネジメントの実践方法を、具体的な解決策を交えて解説した資料をご用意しました。チームのタスク管理におけるよくあるお悩みを解決するヒントが満載ですので、ぜひダウンロードしてお役立てください。
チームワークマネジメント実践のすすめ【資料をダウンロードする】
https://backlog.com/ja/document/backlog-teamworkmanagement/
まとめ:チームビルディングで築いた土台を、チームワークマネジメントで成果に繋げよう
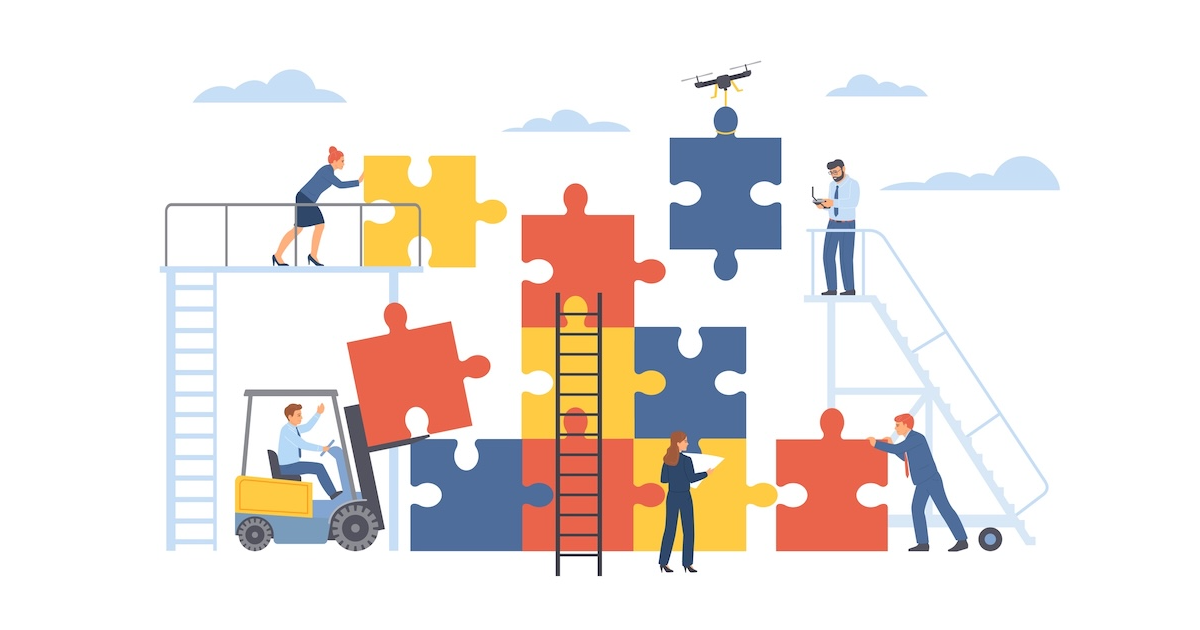
チームビルディングは、メンバー間の信頼関係を築き、同じ目標に向かう一体感を醸成するために不可欠な取り組みです。
この取り組みを成功させるには、まず「チームで達成したい目的を明確に定める」ことが重要です。その上で「メンバー一人ひとりに役割を与え」、それぞれの「適性や相性を考慮してチームを編成する」ことで、個々の能力が最大限に発揮されるようになります。
ただし、チームビルディングはあくまで土台作りに過ぎません。その効果を持続させ、チームとして継続的に高い成果を上げていくためには、日々の業務におけるチームワークマネジメントが重要です。
今回紹介したチームの課題解決のヒントを参考に、ぜひ自社のチーム力向上に役立ててください。より具体的な実践方法は、以下の資料で詳しく解説しています。チームマネジメントに課題を感じている方は、ぜひダウンロードしてお役立てください。
チームワークマネジメント実践のすすめ【資料をダウンロードする】
https://backlog.com/ja/document/backlog-teamworkmanagement/
