新薬開発プロジェクトを大改革!Backlog×「導入支援プログラム」の効果を聞く

Backlog導入前の課題
・Excelによるプロジェクト管理で非効率と属人化が生じていた
・タスク間のつながりや前後の流れを把握できず業務の受け渡しがうまくいかないことがあった
・数十人が集まる会議が「進捗報告の場」になっており、本来の議論ができなかった
Backlog導入後の効果
・導入支援プログラム*の活用で運用ルールや使い方がスムーズに浸透し、社内展開のきっかけにもなった
・タスクの担当者や期限が明確になり、メンバー全員が共通認識を持って自律的に動けるようになった
・Backlog上で進捗を共有する運用が定着し、会議は議論に集中できる場へ変化した
「人にやさしい"くすり"を世界の人びとに」を企業理念に掲げる、医薬品メーカーの株式会社三和化学研究所。同社は新薬開発という長期的かつ複数部門が関わる大規模プロジェクトの管理にBacklogを導入しました。
また、同時に「あんしん!Backlog導入支援プログラム*」を利用することで、スムーズなツール浸透と運用促進を実現。その結果、導入からわずか半年にもかかわらず、全体会議で進捗報告に費やされていた時間がゼロになるなど大きな成果をあげています。
Backlog導入をリードした、新薬開発プロジェクトの事務局を務める経営戦略部 経営企画グループの村瀬氏、小西氏に、劇的な変化に至った秘訣を伺いました。
*現在は「あんしん!Backlog導入支援プログラム 」の提供は行っておりません
目次
医薬品開発プロジェクトの事務局として、Backlog導入をリード
── まずは、御社の事業内容について教えてください。
当社は、糖尿病と腎疾患領域に注力し、医薬品、診断薬の研究開発および製造販売を行う企業です。「健康創造」を事業領域とするスズケングループにおいて、医薬品、診断薬を中心に当社ならではの新しい価値の創造を通じて、社会への貢献を目指しています。
最近では、治療に必要な医薬品が海外では承認されているにもかかわらず、国内では未承認のままとなっている「ドラッグロス」という社会課題に着目し、グループ企業及び業務提携企業との連携によって、国内未承認薬の日本参入を支援する取り組みにも力を入れています。
── お二人の所属部署と、どのような役割を担っているのかもお聞かせください。
私たちの所属は、経営戦略部の経営企画グループです。社内のさまざまなプロジェクトの事務局や、部署横断的な課題に対するハブとしての機能を担っています。今回、Backlogを導入した新薬プロジェクトに関しても、事務局としていろんな部署と関わりながら推進を支援してきました。

株式会社三和化学研究所
経営戦略部 経営企画グループ長
村瀬 貴代 氏
ツールによる一元管理で、部署間コミュニケーションの課題解消を
── 今回、Backlogを導入したのはどのようなプロジェクトなのでしょうか?
社内の新薬開発プロジェクトでBacklogを活用しています。一般的に、新薬を世に出すまでは10年を超える期間を要します。今回のプロジェクトは、上市(研究開発を経て承認された新薬を市販開始すること)が見えてきたフェーズで、研究開発に加えて生産準備や情報提供活動の準備を行う目的で、3ヵ年計画でスタートしました。
研究開発部門がそれまで何年もかけて進めてきた新薬開発の業務を、営業・生産など他部門にも広げていくとなると、スムーズにいかない場面も予想されます。早いタイミングから連携し、全社一丸となって取り組めるようにすることが、プロジェクトの重要なミッションです。
── 期間の長い、大規模なプロジェクトなのですね! Backlogを導入される前は、どのように管理されていましたか?
これまでの新薬開発プロジェクトでは、主にExcelによるスケジュール管理を行っていました。今回のプロジェクト立ち上げにあたり、以前のプロジェクトを参考にしようと社内でヒアリングしたところ、Excelによる管理では多くの課題を抱えがちだったとわかったのです。
具体的には、複数人で同時編集ができずバージョン管理が煩雑になる、タスク間のつながりや前後の流れを把握できず業務の受け渡しがうまくいかない、などの問題があったようです。
さらに、プロジェクトメンバーが集まる全体の定例会議では、いつも進捗報告に終始してしまっていました。さまざまな部署の人が時間を割いて集まるにもかかわらず、十分な議論をする場になっていない点も課題でした。
── そうした課題を解消するために、ツールの導入を検討されたのですね。
はい、その通りです。プロジェクトの進捗を見える化することによって、部署間のコミュニケーションを円滑にしたかったんです。
また、管理職に限らず、一人ひとりのメンバーが各自のタスクだけでなく、ほかのメンバーの担当タスクや全体の流れを見ながら業務を主体的に捉えてほしいという期待もありました。

株式会社三和化学研究所
経営戦略部 経営企画グループ
小西 俊裕 氏
ユーザー数無制限のコストメリットと適切な機能設計が導入のポイント
── プロジェクト管理ツールとして、Backlogを選ばれた経緯についても教えてください。
ツールを探し始めたころ、ビジネス映像メディア「PIVOT」のコンテンツを視聴して、Backlogを知りました。「チームワークマネジメント」の考えが非常に参考になり、強く印象に残っていたんです。比較サイトなどでも検討し、Backlogを含めた3つのサービスをトライアルしてみました。
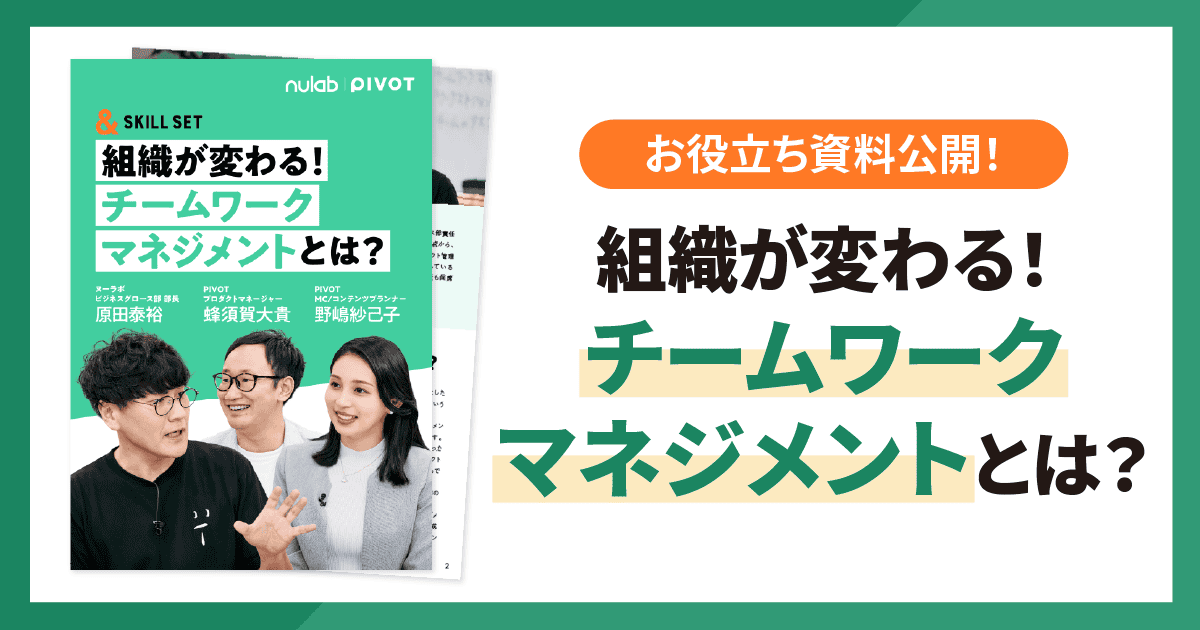
PIVOT動画の内容を凝縮!お役立ち資料「組織が変わる!チームワークマネジメントとは?」を公開しました | Backlogブログ
お役立ち資料「組織が変わる!チームワークマネジメントとは?」を公開しました。今、チームワークマネジメントが必要とされる理由やチームのタスク管…
backlog.com── トライアルの結果、最終的な決め手は何だったのでしょうか?
何よりも大きな決め手になったのは、コスト面での魅力ですね。検討した他社のツールはユーザー課金制でしたが、Backlogはスタンダードプラン以上だとユーザー数が無制限*です。最初に聞いたときは「そんなサービスが本当にあっていいんですか?」と驚きました(笑)。
ユーザーが想定より多くなったとしても、追加で費用が発生しない点が非常にありがたかったです。
*安定した運用を維持するため、最大10,000人までを推奨しています。
── 率直なコメントをありがとうございます!機能面ではいかがでしたか?
Backlogを実際に活用してみると、機能面でも必要な機能が厳選されており、私たちのプロジェクトにフィットすると感じました。機能は、豊富すぎると使いこなせない可能性もあります。一方で、メンバー各々のITリテラシーを問わず、誰にでも使いやすそうなのがBacklogだったんです。
色合いやデザインも好印象で、自然と使いたくなりますし、メンバーの投稿に対してスターを送れる機能も、コミュニケーションツールとして遊び心があって良いなと感じました。こうした理由から、2024年7月よりBacklogを導入しています。
「導入支援プログラム*」活用で、長期プロジェクトの運用基盤構築を目指す
── 三和化学研究所様には、「導入支援プログラム*」も併せてご契約いただきました。
ツールの機能を最大限に引き出すには、初期設定が肝心だと考えました。プロジェクト立ち上げ時の土台をしっかりと固めるために、私たちにとって最適なBacklogの使い方についてアドバイスをいただきたく、導入支援もお願いしたんです。
今回は、3年間という長期にわたる取り組み、かつ数十名が携わる大型プロジェクトです。プロジェクトが進むうちに、当初はメンバー間で合意していたはずの運用方針がだんだん風化してしまい、なあなあになってしまう懸念もあります。
そこで、誰がどのくらいの粒度でどのようにタスクを登録していくか、バラつきの発生を避けるためにも、最初の段階で運用ルールをしっかり決めておこうと考えました。
── 運用ルールの策定に関するサポートへの期待が大きかったのですね。
加えて、これまで使っていたExcel上のガントチャートのデータをBacklogに移行する作業も大変そうだと感じたため、そのレクチャーもお願いしたいと考えていました。
数社トライアルをする中で、他社のツールはサポートいただける範囲が限られているなという印象を受けました。その点、どのツールよりも、ヌーラボの皆さんは「こうした使い方をご希望でしたらこうしましょう」と積極的に提案してくださったのが心強かったですね。
全体会議の内容が激変!「なぜ使うのか」活用の意義も伝えることで、スムーズな浸透に
── Backlogの導入後、どのような効果や変化を感じられましたか?
まず、進捗報告に終始してしまっていたこともあった全体会議が、劇的に変わりました。なんと、単純な進捗報告の時間がゼロになり、今すべき議論に100%集中できるようになったのです。
進捗は「Backlogに書いてあるものを見る」ことが当たり前になったため、わざわざ会議の場で共有する必要がなくなりました。毎月数十名のメンバーが集まり、時間を割いているわけですから、生産性の面でもインパクトが大きかったです。
加えて、参加者間での認識のズレがなくなったことにも驚きました。以前は、同じ会議に出て同じ話を聞いているはずなのに、メンバーそれぞれの認識が少しずつ異なるケースも少なくありませんでした。それが、Backlogを導入してからは、各タスクの担当者や期限を課題登録することで誰もが共通認識を持てるようになったんです。
── 導入支援プログラム*で期待されていた、初期設定や運用ルールの浸透はいかがでしたか?
担当の方には、ExcelからBacklogへのデータ移行について、効率的な進め方を教えていただきました。事務局側としては、想定よりも簡単な作業で済み、大変助かりましたね。
また、担当者の方のご協力をいただき、プロジェクトメンバー向けにBacklogの説明会を実施しました。デモ画面を見せながら基本的な使い方について解説したほか、練習用のプロジェクトも用意し、操作に慣れていってもらいました。
そしてもちろん、当初の目的だったルール策定についても、さまざまなアドバイスをいただきながら固めていきました。しっかりとした環境整備とルールの周知を行ったことにより、早期の運用定着につながったと感じています。事務局の私たちから徹底的にアナウンスした上で、Wikiにも明文化して、いつでも参照できるようにしました。
── 振り返って、とくにどのようなサポートが効果的だと感じられましたか?
メンバーに最初に示したルールは、私たち“Backlog初心者”が手探りで作ったものではなく、サービス提供元でプロジェクト管理のプロでもあるヌーラボの方と一緒に作ったものであったため、納得感や安心感もあり社内のメンバーもすんなりと受け入れてくれました。その点で、社内のメンバーにとっても納得感や安心感があったのではないかと思います。
説明会に関しても、ヌーラボの方に直接わかりやすく説明してもらったことで、理解がより深まりました。これらは、導入支援プログラム*があったからこその効果だったと感じています。
加えて、Backlogを使う意義やBacklogを使って何を実現したいのかといった、根幹のメッセージを伝えることも大切だと、事前にアドバイスをいただいたことが印象深いです。「なぜ」の部分を共有することが、ツールの浸透や効果的な活用を行うための秘訣であると。
Backlogの使い方やルールの周知までは私たちでなんとかできたと思いますが、単にツールの押し付けになってしまい、うまくいかなかったかもしれません。導入支援プログラム*なくしてはこの視点や発想に至らなかったので、本当に感謝しています。
Backlogは、チームワークの醸成に欠かせないコミュニケーションツール
── 今後のBacklog活用について、どのように考えていますか?
現在、社内のさまざまなプロジェクトやタスク管理にもBacklogが活用されるようになってきました。今回のプロジェクトメンバーが広めてくれたり、評判を聞いた他部署の人が導入したりと、経緯はさまざまです。
活用範囲が広がりつつある中で、私たちも全社への浸透を後押しできればと考えています。また、全社での積極的な活用促進と並行して、私たちのようにBacklogの環境整備と利用の後押しを行う、バックログスイーパーを育てていくことが次のステップとして重要だと思っています。最初の土台づくりをしっかりとすれば、社内のメンバーもすぐに操作や課題登録・更新作業に慣れていってくれるはずです。
Backlogは自社のあらゆる場面で使えるツールだと思います。スケジュールやタスクの管理にとどまらず、コミュニケーションツールとしても価値があります。感謝の気持ちを込めてスターを送り合うなど、チームワークを大切にする文化を根付かせていきたいですね。
── 貴重なお話をありがとうございました!
*現在は「あんしん!Backlog導入支援プログラム 」の提供は行っておりません
※掲載内容は取材当時のものです。